横浜市の貸倉庫ガイド
2025/04/07
横浜市は日本を代表する港町としての歴史と魅力を持ちながらも、首都圏の一大経済圏として成長を続けています。
そのため、物品の保管から物流拠点としての活用まで、幅広いニーズに対応できる貸倉庫の需要が高まっています。
しかし、実際に倉庫を借りたり、倉庫を貸し出したりする際には、物件選びや契約条件、法律や補助金制度など、知っておくべきポイントが多岐にわたります。
本記事では、横浜市の貸倉庫に関する専門知識を活かし、「借りたい方」「貸したい方」それぞれの立場に役立つ情報をまとめました。
読者の皆さまが安心してビジネスを展開できるよう、横浜市ならではの特徴と不動産の視点を交えながら、ポイントをわかりやすく解説いたします。

目次
横浜市の貸倉庫が注目される理由:港町と首都圏アクセスの強み
横浜市内の貸倉庫を検討する際、まずはエリアごとの特性を深く理解しておくことが重要です。
都心部・湾岸部・郊外は、それぞれアクセス性や周辺環境、物件規模や費用感に違いがあります。
自社の事業内容や将来的な拡張計画を踏まえて、最適なエリアを選びましょう。
横浜駅・関内周辺エリア
■商業施設やオフィスビルが密集しており、倉庫用地は限られていますが、交通の便が抜群で取引先や顧客へのアクセスがしやすいのが大きなメリットです。
■倉庫スペースが比較的小規模であっても、高付加価値や即日配送ニーズが高い業種に向いています。例えば、ECサイトの商品保管・配送や、小規模商材の在庫拠点として活用するケースが多いでしょう。
■横浜駅・関内周辺エリアは賃料や初期費用が高めになりがちなので、コスト対効果をしっかりと検証することが重要です。また、駐車スペースの確保が難しい場合もあるため、車両での出入りが頻繁な事業には注意が必要です。
湾岸部(ベイエリア)
■港湾施設が集中するエリアで、輸出入を視野に入れた国際物流や大規模保管拠点として活用されるケースが多く見られます。
■大型倉庫や物流拠点が数多く存在し、港湾機能との連携が取りやすい点が魅力です。海上輸送や倉庫間の中継輸送など、広域的なサプライチェーンを構築する企業に適しています。
■一方で、広大な敷地と充実した設備を要する物件が多いため、賃貸条件が高額になる傾向があります。海風や潮害などの影響で建物のメンテナンスコストがかさむ場合もあるため、防錆や防湿対策を含めた長期的視点が必要です。
内陸部(戸塚・港北・青葉など)
■横浜市内陸部エリアは比較的広い土地を確保しやすく、大型倉庫や複数の棟をまとめて借りられる物件が見つかりやすいのが特徴です。
■都心から少し離れる分、賃料や初期費用が抑えられる傾向にあり、コストパフォーマンスを重視する企業にとって魅力的な選択肢と言えます。駐車場や荷捌きスペースを十分確保できる物件も多いため、大型車両を頻繁に出入りさせる物流企業には好適です。
■住宅街に近い場合は、騒音や交通規制に配慮する必要があります。また、従業員の通勤面を考慮するなら、最寄り駅やバス停へのアクセスや、近隣の生活施設の有無も確認しておくと安心です。
以上のように、横浜駅周辺部・湾岸部・内陸部それぞれのエリアは、立地条件や費用、扱う商品・サービス内容に応じて一長一短があります。
どのエリアを選ぶかによって、集客力や輸送効率、ランニングコストなどが大きく変わってくるため、事前の下調べと専門家への相談を活用して、最適な選択肢を見極めましょう。
横浜市の交通アクセスを徹底解説:陸・海・空の要所としての強み
横浜市は東京の南隣に位置し、国内外を結ぶ交通網が非常に発達しています。
倉庫を利用するうえで鍵となるのが、商品や資材の流通をスムーズに行うためのインフラ整備です。
ここでは、陸路・海路・空路それぞれの強みを見ていきましょう。
陸路:高速道路と鉄道網の連携
首都高速道路
首都高速道路は都心部と湾岸部を結ぶ複数の路線網から構成されており、横浜市内では主に横羽線・湾岸線・狩場線などが利用されています。
路線ごとに目的や接続先が異なり、たとえば【横羽線】は東京方面へ直結する幹線ルート、【湾岸線】は羽田空港や川崎エリアを経由しながら東扇島方面へつながるなど、それぞれの特性を踏まえて使い分けることで、高い輸送効率が得られます。
インターチェンジ(IC)の多さも特徴で、渋滞や事故による影響を分散できるため、代替ルートを確保しやすいのがメリットです。
東名高速道路
東名高速道路は東京ICから名古屋方面へ伸びる、国内でも屈指の長距離高速道路です。
横浜市内から最寄りのICとしては、【横浜町田IC】や【青葉IC】などが挙げられ、ここから東京IC・海老名JCT方面へスムーズにつながります。
東名はさらに新東名や伊勢湾岸道とも接続しており、関西圏や中部圏を含む広範囲への輸送に対応可能です。
沿線にはサービスエリアやパーキングエリアが充実しているため、長距離輸送時の休憩・補給拠点としても便利です。
第三京浜
第三京浜道路は横浜市と東京都心部を結ぶ全長約16kmの自動車専用道路です。
横浜新道や首都高速都心環状線などへの接続が容易で、所要時間を短縮しやすいのが魅力。
第三京浜自体は比較的距離が短い路線ですが、大きな渋滞が発生しにくいため安定した走行が可能です。
出口付近の一般道を活用すれば港北ニュータウンや川崎方面へもアクセスしやすく、周辺の物流拠点や倉庫群を利用する際にも役立ちます。
こうした複数の高速道路を組み合わせることで、渋滞や事故などのトラブルを回避する代替ルートを確保しやすく、荷主の納期要望にも柔軟に対応できます。
結果として輸送効率を高め、倉庫運営のコスト削減にもつながるため、横浜市で倉庫を活用する大きなメリットになっています。
JR各線や私鉄各社が縦横に市内をつないでおり、通勤・通学だけでなく小規模配送にも対応しやすい環境が整っています。
鉄道貨物ターミナルも近隣に複数存在するため、遠距離輸送の拠点としても有効活用できます。
海路:港湾都市ならではの輸出入拠点
横浜港は日本屈指の国際貿易港として知られ、コンテナターミナルやロロ船(車両航送船)など、多様な船舶に対応可能な施設がそろっています。
大規模な海上輸送を前提とした荷物の保管・移送を考える場合、港湾近くの倉庫は圧倒的に有利です。
港湾関連の各種サービス(通関手続き、検疫、倉庫内での保管・仕分け業務など)が集積しているため、輸出入手続きをスピーディに進められるのも魅力です。
空路:羽田空港や成田空港へのアクセス
横浜市内から首都高速湾岸線を使えば、羽田空港へは車で30分前後と近距離のため、航空貨物との連携も容易です。
国内外への緊急輸送が求められるビジネスにも対応しやすい環境と言えます。
成田空港へはやや距離があるものの、高速道路網や鉄道(成田エクスプレスなど)を活用すれば十分カバーできる範囲です。
航空貨物の大規模拠点として、成田方面へ荷物を送る際もスムーズに行えます。
こうした陸・海・空の交通インフラをフルに活用できる点が、横浜市で貸倉庫を利用する大きなメリットです。
物流の多角化が進む現代では、輸送手段を複数持つことが企業競争力の向上につながります。
倉庫を選ぶ段階で、自社が主に利用するルートを念頭に置き、最寄りのインターチェンジや駅、港湾施設への距離や移動時間を比較検討するとよいでしょう。
貸したい方へ:倉庫活用術:需要動向と差別化戦略
横浜市内には歴史ある建物や、工場跡地をリノベーションして倉庫として再生させるケースも増えています。
空き倉庫の資産価値を高めるには、まずマーケットのニーズを把握することが先決です。
EC事業やイベント関連企業は大容量かつ搬出入が容易な物件を求める一方、オフィス機能を併せ持つ“倉庫兼ショールーム”のような多機能スペースへの需要も見逃せません。
活用用途の幅を広げることで、差別化と収益向上を図ることができます。
倉庫運営のリスクマネジメント:防災・防犯対策と保険の重要性
港町として地形的な特徴を持つ横浜市では、台風や豪雨による浸水リスクにも注意が必要です。
倉庫内の設備や荷物の損害を最小限に抑えるため、排水設備の点検、防犯カメラや警備システムの導入を検討しましょう。
また、火災・盗難・災害などに備えた保険契約を結んでおけば、万一の事故があっても経済的被害を抑えられます。
賃借人と賃貸人それぞれの責任分担も、契約時に明確にしておくと安心です。
横浜市のハザードマップで確認する災害リスク
貸倉庫を契約する前に、所在地の災害リスクを把握しておくのは非常に重要です。
横浜市では、さまざまな災害に対応したハザードマップが公開されています。
以下の8つを押さえておくと、物件立地の安全性を総合的に判断できます。
洪水(河川氾濫)
マップの名称: 浸水ハザードマップ(洪水・内水・高潮を一括で確認できる場合もあり)
確認サイト:
横浜市公式サイト「浸水ハザードマップ」
国土交通省「ハザードマップポータルサイト(重ねるハザードマップ)」
チェックポイント
■色分けされた浸水想定区域に物件が含まれていないか
■浸水深(0.5m・3mなど)と想定される被害規模
■避難所や指定緊急避難場所が近くにあるか
洪水の浸水深が大きいエリアに倉庫を構える場合、1階の在庫や設備が水没するリスクが高まります。
ハザードマップで色が濃いほど深刻な浸水が想定されるので要注意。
内水氾濫(都市型水害)
マップの名称: 同上(浸水ハザードマップで一括表示されるケースが多い)
確認サイト:
横浜市公式サイト「浸水ハザードマップ」
チェックポイント
■河川から離れていても色分けされた浸水想定に入っていないか
■下水道が処理しきれない豪雨時に床下浸水の恐れがあるか
内水氾濫は短時間の大雨で道路や敷地内が冠水する現象。
大きな河川がない場所でも意外にリスクが高いことがあるので、周辺の地形や排水状況を地図から確認しましょう。
高潮
マップの名称: 浸水ハザードマップ(高潮)
確認サイト:
横浜市公式サイト「浸水ハザードマップ」/神奈川県公表の高潮浸水想定図
チェックポイント
■海岸や河口付近の低地が浸水想定域になっていないか
■想定される浸水深(1m未満/2m以上 等)
台風で潮位が上昇し、防潮堤を越えると瞬く間に浸水被害が広がるケースも。
沿岸部や河川近くの埋立地は特に確認を。
津波
マップの名称: 津波ハザードマップ(津波浸水想定図)
確認サイト:
神奈川県公式サイト(地域別の浸水想定図)/横浜市の津波避難施設情報
チェックポイント
■沿岸エリアや運河沿いで、津波浸水想定区域内かどうか
■津波の想定浸水深、最寄りの津波避難施設(建物)の場所
倉庫は港湾付近に多いものの、津波リスクは地形のわずかな高低差で浸水被害が変わる場合があります。
海抜や近隣の避難ビルも要チェック。
土砂災害(がけ崩れ・土石流)
マップの名称: 土砂災害ハザードマップ
確認サイト:
横浜市公式サイト(区別のPDF)、神奈川県「土砂災害情報ポータル」
チェックポイント
■土砂災害警戒区域(イエローゾーン)・特別警戒区域(レッドゾーン)にかかっていないか
■近くにがけ地や急斜面がある場合は特に注意
倉庫が斜面のすぐ下にある場合、豪雨時に土砂崩れの危険性大。
レッドゾーンは建物倒壊被害が想定される深刻なエリアです。
液状化現象
マップの名称: 横浜市「液状化マップ」
確認サイト:
横浜市公式サイト「地震被害想定調査」のページで、地盤の液状化危険度を閲覧
チェックポイント
■埋立地や低地で、液状化危険度が高い(赤・オレンジ)のエリアに該当していないか
■想定地震の種類ごとに危険度が変わるので、最悪ケースで評価
液状化で地盤が沈下・傾斜すると、建物が使えなくなる可能性あり。
広域の地図でざっくり確認し、特に危険度が高い場所は避けるのが無難です。
地震の揺れ・建物倒壊リスク
マップの名称: 横浜市地震マップ(想定震度分布図)
確認サイト:
横浜市公式サイト(区単位の震度分布PDFを提供)
チェックポイント
■強い揺れが想定される場所(震度6強~7)かどうか
■古い建物だと倒壊リスクが高まるため、耐震性能との兼ね合いも要検討
埋立地沿いは軟弱地盤で揺れが増幅されやすい。
震度マップを見て、特に赤や濃い色が付いているエリアであれば、建物の耐震診断をしっかり確認しましょう。
火災(延焼リスクが高い木造密集地域)
マップの名称: 不燃化推進地域等の指定図(iマッピーなど行政地図から閲覧)
確認サイト:
横浜市建築局ホームページ/行政地図情報(iマッピー)
チェックポイント
■物件周辺が木造住宅密集地に該当していないか
■「地震火災対策重点地域」や「不燃化推進地域」に指定されていないか
木造住宅が多い狭い路地では延焼拡大リスクが高く、消防車の進入が難しい場合も。
倉庫が燃え広がりの原因になる可能性もあるため、火災保険・防火対策を念入りに。
ハザードマップ確認の流れ
候補物件の住所を把握
■正確な町名・番地まで確認。地図上でどこに位置するか、最寄りの河川・海岸線・丘陵を意識。
市公式サイトなどで複数のハザードマップを入手
■横浜市公式サイト、神奈川県、国土交通省ハザードマップポータルを使う
■「洪水・内水・高潮」「土砂災害」「津波」「液状化」「地震」のファイルをダウンロードまたはブラウザ表示
各マップ上で物件の場所を検索
■メインの道路・鉄道・地形などを手がかりに、候補物件を探す
■ズームし過ぎず、広範囲も含めて周囲の状況を確認(近隣に危険斜面や浸水低地がないか)
色分けや凡例、想定規模をチェック
■浸水深や震度、危険度ランクがどの段階か
■想定される最大規模(「最大クラスの豪雨・地震」など)のシナリオを確認
避難所や避難ルートの把握
■もし想定区域内の場合、緊急時に周辺住民はどこに避難するか
■道路や橋が寸断される可能性があるか、徒歩で安全な場所へ移動できるかをイメージ
総合判断し、専門家への相談も
■リスクが高い区域なら別の物件を検討、あるいは賃貸契約時に防災対策を検討
■不動産会社や行政窓口、建築専門家に詳細を確認し、最終判断を下す
横浜市のハザードマップは、洪水や津波、土砂災害、液状化、地震、火災など多岐にわたるリスクを「地図」に落とし込み、色分けや図表で分かりやすく可視化しています。
貸倉庫を契約する前に、こうしたリスクをしっかり把握しておけば、大きな被害を回避できる可能性が格段に高まります。
■浸水リスク(洪水・内水・高潮・津波)については、「どの範囲まで水が来るか」「想定水深はどのくらいか」のチェックが第一。
■土砂災害や液状化は土地の性質が大きく影響し、建物の被害リスクや長期運用への支障が顕在化しやすい点に留意。
■地震時には揺れやすさと周辺火災リスクが鍵。災害時の避難ルートが確保できるかも含め、事前対策を検討するのがおすすめです。
ハザードマップはあくまでも想定に基づいた資料であり、実際の被害状況は想定を上回る可能性もあります。
とはいえ、不動産契約においては「リスクをゼロにする」ことよりも「情報を十分に把握し、リスクを最小化する行動」が重要です。
各マップで得た知見を踏まえ、信頼できる不動産会社や専門家と連携しながら、安全性の高い貸倉庫を選択してください。
まとめ
本記事では、横浜市の貸倉庫に関する専門的な視点と、借りたい方・貸したい方双方に役立つ情報を中心に解説しました。
横浜市は物流・商業の要所としての潜在力が高く、適切な物件選びや法律・規制への対応、そして賢い投資や運営を行うことで、安定したビジネスを実現しやすいエリアといえます。
読者の皆さまが、この記事をきっかけに横浜市の貸倉庫の魅力や活用ポイントを理解し、安心してビジネス展開を進められることを願っています。
立和コーポレーションでは、貸倉庫についての専門性を活かしながら、お客様に安心してお取引いただける企業を目指しております。
横浜市内の貸倉庫について、是非お気軽にお問合せください。
宅地建物取引業 国土交通大臣免許(3)8600号
◆この記事に掲載の情報は、執筆者の個人的見解であり、立和コーポレーションの見解を示すものではありません。
◆この記事に掲載の情報の正確性・完全性については、執筆者および立和コーポレーションが保証するものではありません。
◆この記事に掲載の情報は、執筆時点のもので、最新の情報ではない可能性があります。
◆この記事に掲載の情報を利用したことにより発生するいかなる費用または損害等について、執筆者および立和コーポレーションは一切責任を負いません。
あらかじめご了承ください。

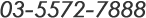
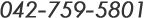
 前の記事
前の記事




