2025年4月施行|改正物流法のポイント
2025/02/25
2025年4月1日から施行される改正物流法。
本記事では、改正の背景や具体的な変更点、企業が受ける影響について詳しく解説し、どのような対応策が求められるのかを整理します。

背景と改正の必要性
労働力不足と環境負荷低減
日本の物流業界では、トラックドライバーの高齢化や人手不足が深刻化しています。
これに伴い、2024年問題(労働時間の上限規制による輸送能力の低下)が現実味を帯びてきました。
さらに、CO₂排出量の削減も国際的な課題となっており、より効率的な物流システムの構築が求められています。
サプライチェーンの見直しと効率化ニーズ
物流の停滞は、経済全体の生産性に影響を与える要因となります。
サプライチェーンの効率化は、企業の競争力強化だけでなく、持続可能な社会の実現に向けた重要な課題です。
改正物流法は、これらの問題を解決し、安定的で効率的な物流ネットワークを整備する目的で制定されました。
改正物流法とは
改正の概要
法改正の背景
「2024年問題」に対処し、物流業界全体の健全な成長を促すために改正物流法が導入されました。
また、軽トラック事業者による事故増加も課題とされ、安全対策の強化が求められています。
主な改正点
改正物流法では、以下の点が強化・追加されます。
■荷主・物流事業者への努力義務の導入
物流効率化を促進するため、荷待ち時間短縮や積載率向上に向けた取り組みが求められる。
これにより、輸送コストの削減や環境負荷の低減が期待され、業界全体の生産性向上に寄与することが目的とされている。
■運送契約の書面交付義務の強化
運送契約の透明性を高めるため、書面または電子データでの契約内容の明示が義務化される。
これにより、取引条件の適正化が促進され、不当な契約変更やトラブルを未然に防ぐことが期待される。
■軽トラック事業者への安全管理者選任義務の追加
軽トラック事業者に対して、事故防止や運行管理の強化を目的とした安全管理者の選任が義務付けられる。
これにより、適切な安全対策の実施が求められ、事業者の安全責任が明確化される。
施行までのスケジュール
■施行日:2025年4月1日
■施行前後の準備項目:
・荷主・物流事業者は、荷待ち・荷役時間の短縮、積載率向上の施策を準備する。
・運送契約の適正化や安全管理体制の整備が求められる。
主な改正ポイント
1. 荷主・物流事業者への努力義務
■内容:荷待ち時間の短縮、積載率向上など、物流効率化を促進。
■詳細:企業は輸送計画を見直し、荷積みの効率化や待機時間の短縮を実施する必要がある。
■対象:全ての荷主・物流事業者。
2. 運送契約の書面交付義務
■内容:運送契約締結時に、サービス内容や料金を明記した書面を交付する義務。
■対象:荷主、トラック事業者、利用運送事業者。
3. 軽トラック事業者への規制強化
■内容:安全管理者の選任や講習受講、事故報告の義務化。
■対象:軽トラック事業者。
4. 特定事業者への追加義務
■内容:一定規模以上の荷主・物流事業者は、中長期計画の策定、定期報告、物流統括管理者の選任が必要。
■対象:年間9万トン以上の貨物を取り扱う荷主。
対象となる企業・事業者
対象業種・業態
■物流・運送業者
■自社配送を行うメーカーや小売業
■自社の物流機能を外注している企業
企業規模による影響の違い
■大企業:中長期計画の策定、物流統括管理者の選任が義務付けられる。
■中小企業:努力義務の対象となり、物流効率化の取り組みが求められる。
施行後の展望とメリット
企業側のメリット
■物流の効率化によりコスト削減
物流の最適化により、無駄な輸送コストを削減し、燃料費や人件費を抑えることができる。
特に、共同配送の活用や荷待ち時間の短縮が鍵となり、サプライチェーン全体の利益向上につながる。
■サービスレベル向上
物流の迅速化や確実な配送を実現することで、顧客満足度の向上につながる。
特に、適切な在庫管理や配送の精度向上により、供給の安定化が期待され、企業の信頼性強化にも寄与する。
業界全体の変革
■共同配送や在庫集約の推進により環境負荷を軽減
企業間の協力による共同配送は、トラックの稼働率を向上させ、無駄な走行を削減することでCO₂排出量を抑える。
適切な在庫管理と集約によって輸送の効率化が図られ、持続可能な物流体制の実現につながる。
労働環境改善
■ドライバーの長時間労働削減
労働時間の適正化により、過労による事故リスクを低減し、ドライバーの健康維持を促進する。
これに伴い、企業は運行計画の見直しや、休憩時間の確保を徹底し、安全で持続可能な労働環境の整備が求められる。
■職場環境の向上
労働環境の改善により、ドライバーの負担軽減や職場の安全性が向上する。
企業は従業員の福利厚生や休憩施設の整備を進め、働きやすい環境を提供することで、従業員の定着率向上にもつなげることができる。
まとめ
改正物流法は、物流業界の課題解決を目的として導入され、特に労働環境の改善や業務の効率化に重点を置いています。
企業は、荷待ち時間の短縮や契約内容の明確化などの対策を講じる必要があります。
大企業は中長期計画の策定が義務付けられ、中小企業も物流の合理化が求められます。
適切な対応を行うことで、コスト削減や持続可能な物流体制の構築につながり、業界全体の発展に寄与することが期待されます。
本記事では、2025年4月に施行される改正物流法について、背景や具体的な変更点、企業が取るべき対策について詳しく解説しました。
企業が適切に対応するためには、早めに準備を進めることが重要です。
宅地建物取引業 国土交通大臣免許(3)8600号
◆この記事に掲載の情報は、執筆者の個人的見解であり、立和コーポレーションの見解を示すものではありません。
◆この記事に掲載の情報の正確性・完全性については、執筆者および立和コーポレーションが保証するものではありません。
◆この記事に掲載の情報は、執筆時点のもので、最新の情報ではない可能性があります。
◆この記事に掲載の情報を利用したことにより発生するいかなる費用または損害等について、執筆者および立和コーポレーションは一切責任を負いません。
あらかじめご了承ください。
対象都道府県=
北海道・青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県・茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・山梨県・長野県・新潟県・富山県・石川県・福井県・岐阜県・静岡県・愛知県・三重県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県・鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県・徳島県・香川県・愛媛県・高知県・福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県
対象物件種目=
貸工場・貸倉庫・貸地・売工場・売倉庫・売事業用地

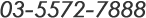
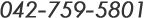
 前の記事
前の記事




