江東区の貸工場ガイド
2025/02/26
東京都の湾岸エリアに位置する江東区は、東京の主要ビジネス拠点の一角を担う都市の一つです。
ここでは、江東区で貸工場を探す際に押さえておきたい情報を整理し、客観的な視点から、交通アクセスや工場エリアの特徴、そして市場動向や補助金情報などをまとめました。
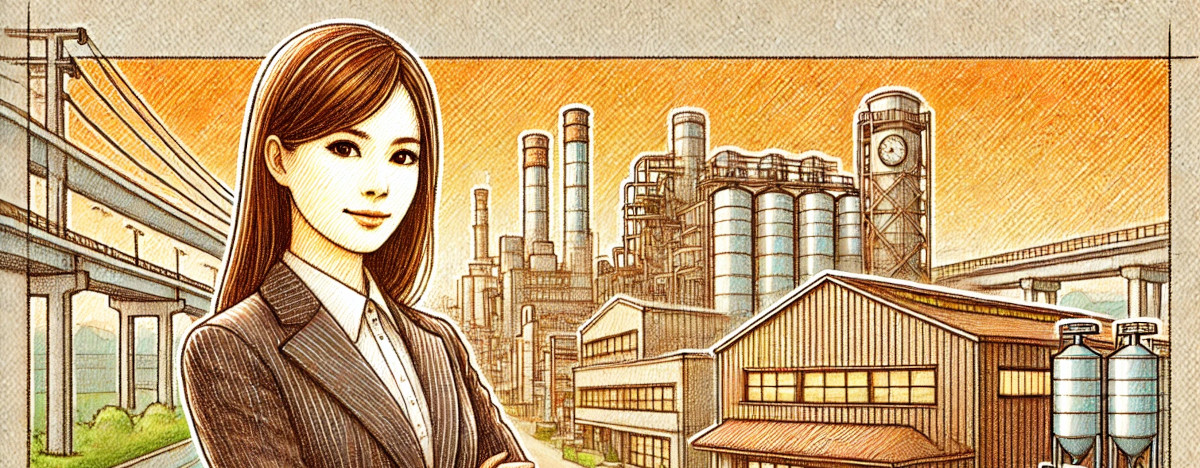
目次
江東区の主要となる交通アクセス
高速道路の特徴・利便性
江東区は首都高速道路をはじめ、湾岸エリアの交通網が発達しています。
特に首都高速湾岸線(B)、9号深川線(9)、7号小松川線(7)が区内を通り、都心や千葉方面へのアクセスが良好です。
主要港や羽田空港、成田空港への移動もスムーズで、製造業や物流業にとって大きなメリットがあります。
主要な高速道路の詳細
ルート 東京港エリアを経由し、千葉・神奈川方面へ接続。
特長 物流業務の基幹ルートで、大型車両の利用が多い。
利点 東京港のコンテナターミナルと連携しやすく、港湾物流に最適。
ルート 江東区中心部を縦断し、中央区・千代田区方面へ直結。
特長 都心方面へのアクセスが良好で、営業拠点との連携が容易。
利点 小規模製造業や都市型物流拠点の立地に適している。
ルート 荒川沿いを走り、東京都東部と千葉県を結ぶ。
特長 環状七号線と接続し、内陸部への物流ルートとして機能。
利点 郊外や関東圏内の他地域への輸送を考える企業に適している。
その他の主要道路
国道357号(東京湾岸道路)
湾岸エリアの主要幹線道路として機能し、各工業エリアや倉庫地帯と直結。
環状七号線(環七)
江東区から東京都内の多方面へアクセス可能で、都市内の物流に適している。
江東区の高速道路網は、港湾物流・都市型製造業・小規模工場のそれぞれのニーズに対応しやすい構造となっています。
ただし、交通量が多い時間帯には渋滞が発生しやすいため、物流計画の際には時間帯別の輸送ルートの検討が重要になります。
鉄道・港湾アクセス
鉄道(JR・私鉄など)江東区内には複数の鉄道路線が走っており、都心部へのアクセスや近隣エリアとの移動がスムーズに行えます。
鉄道輸送は主に旅客輸送が中心ですが、物流や企業活動にも活用されています。
以下、主要路線の概要を説明します。
主な駅 越中島駅・潮見駅・新木場駅
特徴 東京都心(東京駅)と千葉県方面を結ぶ主要幹線。新木場駅で東京メトロ有楽町線・りんかい線と接続し、湾岸エリアの物流・製造拠点として活用される。
主な駅 東陽町駅・南砂町駅
特徴 東京都心と千葉方面を結ぶ主要地下鉄。沿線には住宅地やオフィス街が多く、従業員の通勤利便性が高い。
主な駅 大島駅・西大島駅
特徴 新宿方面へ直通し、都心部との移動が容易。特に市ヶ谷や新宿方面の企業との連携を強化したい企業に向いている。
主な駅 新木場駅
特徴 湾岸エリアの物流拠点や工場エリアへのアクセスを担う重要な路線。貨物輸送にも利用されることがある。
主な駅 有明・豊洲・青海
特徴 臨海副都心エリアを網羅し、都市型工場やハイテク産業の進出が進むエリアと連携可能。
鉄道アクセスの利便性と活用ポイント
都心部へのアクセスが良好
東京メトロ東西線や都営新宿線を活用することで、都心部の企業やオフィスとの連携がしやすい。
臨海エリアとの連携
JR京葉線・りんかい線を利用すれば、物流・倉庫・工業エリアへのアクセスがスムーズ。
従業員の通勤利便性が高い
各駅周辺には住宅地や商業施設が整備されており、労働力の確保がしやすい環境が整っている。
このように、江東区の鉄道網は物流やビジネス活動だけでなく、従業員の通勤環境の整備にも寄与しているため、企業にとって利便性の高いエリアといえます。
港湾(東京港)
東京港の一部を擁する江東区は、国内外への海上輸送が活発に行われています。
コンテナターミナルや倉庫が多数分布しているため、輸出入を伴う工場にとってはロジスティクスの利点が大きいといえます。
全体として、江東区は首都高や鉄道網、港湾をまとめて利用できる立地が魅力ですが、一方で交通量が多い時間帯の渋滞や混雑にも留意しておく必要があるでしょう。
江東区の工場エリアの特徴・魅力
工場エリアの分布や規模
江東区は、埋め立てにより拡張された土地が多く、湾岸部を中心に工業団地や倉庫が点在しています。
一方で、区内には商業地・住宅地も多く混在しているため、大規模工場と中小規模の町工場が混在するのが特徴です。
臨海部エリア江東区の臨海部は、埋め立てにより形成された広大な工業用地が広がり、主に物流・倉庫・製造業の拠点として発展してきました。
特に、新木場、東雲、有明、青海などのエリアは、大規模な物流センターや製造施設が集積し、港湾機能とも連携しやすい立地条件を備えています。
新木場エリア もともと木材産業が盛んで、現在も加工業や倉庫業が多い。鉄道・首都高速へのアクセスが良好。
東雲エリア 大型商業施設も増えつつあるが、倉庫や物流センターが集中するエリア。
有明エリア 再開発が進む一方で、依然として港湾物流や関連製造業の拠点が点在。
青海エリア 東京港に隣接し、コンテナターミナルや国際物流拠点として機能。
交通インフラの利便性
・首都高速湾岸線・東京港臨海道路を活用した陸上輸送の利便性が高い。
・東京港のコンテナターミナルが近く、海上輸送を活用した物流戦略を組みやすい。
・新木場駅・有明駅などの鉄道アクセスがあり、従業員の通勤利便性が確保しやすい。
これらの要素から、江東区の臨海部エリアは、港湾を活用した輸送、倉庫業、製造業の拠点として引き続き重要な役割を担っています。
内陸部エリア古くからの町工場が残り、住宅街との近接も多いため、騒音や排水に対する配慮が必要となるケースも。
産業クラスターが形成されている地域の概要
東雲・新木場周辺港湾アクセスを活かした倉庫・物流拠点が多く、大型の製造・加工施設も見られます。
深川エリア歴史ある下町文化の中に、古くからの中小規模の製造業が点在。食品関連や小ロットの加工業などが多いイメージです。
なぜそのエリアに工場が集まっているか
歴史的経緯と埋め立て地の活用東京湾の埋め立て事業が進む中で、広大な工業用地として整備されてきた背景があります。
交通インフラの充実首都高や鉄道、東京港など多面的な交通網が整備されており、物流効率の観点で優位性がある。
行政や公的機関の支援近年は、製造業だけでなくITや物流企業など、新たな産業の呼び込みにも力を入れています。
江東区の貸工場の需要と供給
市場動向
首都圏全体で工業用地のニーズが一定数あるなか、とりわけ交通インフラや港湾に近い江東区は安定的な需要が続いている状況です。
近年では、再開発が進むエリアにおいて新たな産業の誘致が進む一方、既存の製造業エリアでは賃料の上昇や用途変更が見られるケースもあります。
江東区の貸工場市場の特徴
賃料の上昇傾向
江東区の貸工場は、東京都心近郊の工業エリアの中でも安定した賃料を維持していたが、近年の再開発や物流拠点の増加により、賃料の上昇が顕著になりつつある。
特に、新築や設備が充実した物件では、賃料が周辺相場よりも高くなる傾向がある。
工場用地の用途転換
物流拠点や商業施設の開発が進むにつれ、工場向けの物件供給が減少している。
一部の工場跡地がオフィスビルや住宅用地へと転用され、製造業向けの大型物件の確保が困難になりつつある。
物流・倉庫業との競争
江東区は物流拠点としての需要が高まっており、倉庫業者が積極的に物件を取得するケースが増加。
これにより、工場向けの物件供給が相対的に減少し、製造業者にとって競争が激化。
物流との競争を見据えた戦略を練る
物流業界の需要拡大が続くなか、製造業としては適切な立地や運営計画を考慮しながら物件選定を行う必要がある。
江東区は引き続き、製造業と物流業の双方にとって重要な拠点となるが、今後はより高付加価値製品の製造や都市型製造業にシフトする企業が増えると予想される。
適切な物件選定と市場動向の把握が、今後の事業展開において重要な要素となる。
競合状況
他の湾岸エリアとの比較大田区や品川区など、都心と港湾に近い地域は総じて賃料が上がりやすい傾向があります。
築年数・設備面の差借り手としては建物の老朽化や床荷重、天井高などを重視するため、最新設備を備えた物件は高値になりがちです。
賃料や設備要件を総合的に検討しながら、周辺自治体も含めた情報収集を行うと、より幅広い選択肢を得られるでしょう。
江東区の補助金・助成金情報
江東区や東京都、国による企業誘致策や設備投資支援を活用することで、コスト削減や資金調達のハードルを下げられる可能性があります。
年度ごとに条件や金額が変動するため、最新の情報をチェックしましょう。
活用時のポイント・注意点
スケジュール管理申請期間や審査期間が限定的な場合も多いため、早めのリサーチが欠かせません。
要件の詳細確認従業員数や事業規模、使途などで対象外となる可能性があるので、募集要項をしっかり読み込む必要があります。
専門家の活用申請書類の作成は煩雑になりがちです。必要に応じて行政書士や中小企業診断士に相談することで、手続きの効率化や成功率向上が期待できます。
江東区の今後の市場動向の簡単な展望
江東区における製造業・工場需要の見通し
グローバル競争が激化する一方で、海外輸送費の高騰や生産拠点の分散化などにより、国内回帰や都市型製造への関心が高まる可能性があります。
湾岸エリアに立地する江東区は、この流れを受けて堅調な需要が続くと予想されます。
企業が貸工場の賃借を検討する際の視点
経営者の視点
立地コストと交通利便性のバランスをチェック
用途地域・建築規制を踏まえた設備導入計画の策定
従業員の視点
通勤のしやすさ、周辺の住環境
職場環境(作業環境、安全性、セキュリティなど)の確保
地域社会の視点
騒音や排水などの環境への影響を管理し、住民や近隣企業とのトラブルを回避
地元経済への貢献や産学連携など、地域との共存を意識
江東区の産業エリアとしての歴史
江東区は、古くから東京の物流・製造業の中心地として発展してきました。
江戸時代から水運を利用した物資の集積地として栄え、近代に入ると埋め立て事業の進展とともに工業エリアが形成されていきました。
以下、江東区の産業の歴史を年表形式で整理します。
江戸時代
隅田川・荒川を活用した水運業が発展し、木材・米・魚介類などの集積地となる。
明治時代
近代化の進展に伴い、倉庫業・造船業・食品加工業が発展。湾岸部の埋め立てが始まる。
大正時代
工業地域としての発展が進み、鉄鋼・化学工業などの重工業が進出。
昭和前期
戦時体制により軍需産業が発展。戦後は復興需要を背景に製造業が再興。
高度成長期
東京湾岸の埋め立てが加速し、大型工場・物流センターが建設される。
バブル期
豊洲・東雲・有明エリアの再開発が本格化し、商業施設が増加。
2000年代
物流拠点化が進み、都市型製造業・IT関連企業の進出が見られる。
現在
港湾物流の発展とともに、都市型産業の拠点としての機能が強化されている。
江東区の産業発展の背景
水運を活かした物流の発展江東区は、江戸時代から隅田川・荒川・東京湾を活用した物流拠点として発展してきました。
江戸期には木材や穀物の流通拠点となり、現在も倉庫業・物流業が盛んなエリアです。
埋め立て地の開発による工業発展明治以降、臨海部の埋め立てが進み、大規模な工場や倉庫が立地可能な土地が整備されました。
特に戦後の高度成長期には、製造業の発展が著しく、東京湾岸の工業地帯としての地位を確立しました。
戦後の復興と経済成長戦後復興の時期には、食品加工業・印刷業・金属加工業などの中小企業が活躍し、地域経済の支えとなりました。
これにより、製造業の集積地としての特徴が強まりました。
物流業への転換と再開発の進展高度成長期以降、江東区は物流業の拠点としての役割を強め、大型倉庫や物流センターが増加しました。
近年では豊洲・東雲・有明エリアの再開発が進み、製造業から物流業、商業施設への転換が見られています。
現在の江東区は、製造業だけでなく、物流業や都市型産業の拠点として発展を続けており、今後も新たな産業の集積地としての可能性が高まっています。
まとめ
江東区で貸工場を探す際は、首都高や鉄道、港湾といった交通インフラが充実している利点と、住宅地との近接から生じる環境規制の両面をしっかり把握することが重要です。
また、補助金・助成金などの公的支援策をうまく活用すれば、設備投資や事業拡大のハードルを下げられるかもしれません。
湾岸エリアとして伝統的に物流や倉庫、製造業が多い江東区は、今後も都心近郊での生産・加工拠点として安定した需要が見込まれます。
一方で、地価や賃料の上昇や再開発による影響など、変化の要素も大きいエリアであるため、常に最新の情報を収集しながら最適な立地を見極めることが肝要です。
宅地建物取引業 国土交通大臣免許(3)8600号
◆この記事に掲載の情報は、執筆者の個人的見解であり、立和コーポレーションの見解を示すものではありません。
◆この記事に掲載の情報の正確性・完全性については、執筆者および立和コーポレーションが保証するものではありません。
◆この記事に掲載の情報は、執筆時点のもので、最新の情報ではない可能性があります。
◆この記事に掲載の情報を利用したことにより発生するいかなる費用または損害等について、執筆者および立和コーポレーションは一切責任を負いません。
あらかじめご了承ください。

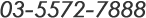
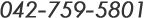
 前の記事
前の記事




