貸工場・貸倉庫・売工場・売倉庫におけるエレベーター設備の重要性とは|種類・価格・法令・点検の基礎知識
2025/07/18
貸工場・貸倉庫・売工場・売倉庫を選ぶ際、建物の構造や立地に注目する方は多いかと思います。
しかし、実務面で大きな差となるのが、「エレベーター(荷物用リフト)」の有無とその性能です。
階層のある工場や倉庫では、荷物の上下搬送が日常的に発生します。
こうした場面で昇降機器が整っているかどうかは、作業効率、安全性、法令遵守、そして長期的な設備維持コストにも直結します。
本記事では、エレベーター・リフト付きの工場・倉庫を検討する際に押さえておきたい基礎知識として、設備の種類や導入価格、関係法令、点検義務などを専門的かつわかりやすく解説します。

目次
エレベーター・リフト付き工場・倉庫物件の希少性
多くの工場・倉庫は荷物の大量移動を前提に設計されていますが、実はエレベーターやリフトが常設された貸工場・貸倉庫・売工場・売倉庫は非常に希少です。
特に都市部では敷地制限から2階建て以上の物件が多く見られる一方で、階層間の搬送設備が十分に整っていないケースも少なくありません。
エレベーターや荷物用リフトは、重量物や長尺物の上下移動を安全かつ効率的に行うための重要な設備です。
荷下ろし時の事故リスクを軽減し、作業時間の短縮にも寄与することから、特に製造業や物流業においては「導入済み」であること自体が大きな付加価値となります。
はい、承知いたしました。ご提示いただいた記事を、より分かりやすく、専門性を高める方向でブラッシュアップしました。
工場・倉庫の垂直搬送を効率化!主な設備の種類と特徴
工場や倉庫において、上下階への荷物の移動は、保管効率や作業生産性を左右する重要な要素です。
ここでは、一般的なエレベーター以外の、荷物搬送に特化した代表的な設備の種類と、それぞれの特徴・用途を解説します。
荷物用エレベーター
荷物専用に設計された、堅牢な昇降機です。建築基準法上の「エレベーター」に該当し、高い安全基準が求められます。
主な特徴
用途は荷物のみで、人の搭乗は法律で禁止されています。
数百kgから数トンまで、幅広い耐荷重に対応可能です。
フォークリフトが直接乗り入れて荷役作業ができる、堅牢な構造のタイプもあります。
最適な用途
重量物やパレット単位の荷物を、安全かつ確実に複数のフロアへ搬送したい場合。
垂直搬送機・簡易リフト
比較的シンプルな構造で、低コスト・短工期で導入できる昇降機です。
主な特徴
多くの場合、建築基準法上の「エレベーター」には該当せず、「簡易リフト」として扱われます。
法定点検や確認申請が不要なケースもありますが、その分、使用者側での主体的な安全管理が不可欠です。
設置の自由度が高い反面、安全装置などがエレベーターに比べて簡素な傾向があります。
最適な用途
2〜3階建ての倉庫などで、比較的軽量な段ボールケースなどを低頻度で上げ下げする場合。
垂直連続搬送機(バーチカルコンベヤ)
コンベヤラインに組み込み、荷物の垂直方向への連続的な自動搬送を実現する設備です。
主な特徴
床面のコンベヤと連携し、搬送プロセスを完全自動化できます。
高速かつ大量の荷物を連続的に処理できるため、仕分け・搬送能力が飛躍的に向上します。
省人化やリードタイム短縮に大きく貢献します。
最適な用途
大規模な物流センターや自動化された工場で、荷物を無人で高速に仕分け・搬送するラインに組み込む場合。
導入・維持にかかるコストと価格感
エレベーターやリフトを新設または更新する際には、数百万円から1,000万円を超えることも珍しくありません。
とくに中量~重量対応の荷物用エレベーターでは、建物の構造補強やシャフト設置工事などを伴い、導入コストが嵩む傾向にあります。
また、導入後も年次の法定点検や部品交換、修繕など継続的なメンテナンス費用が発生します。
平均的には年間10万円~30万円程度の維持費がかかると言われています。
特に賃貸物件の場合、老朽化した設備が「残置物」とされ、借主に更新や撤去の負担が発生するケースもあるため、契約前の確認が重要です。
関連法令と点検義務
荷物用エレベーターや簡易リフトなどの昇降設備を安全に運用するためには、関連法令の遵守が不可欠です。
これらの規定は、単なる手続きではなく、労働災害を未然に防ぎ、企業の責任を果たすための重要な基盤となります。
主に「建築基準法」と「労働安全衛生法」の2つの法律が関わってきます。
建築基準法に基づく「定期検査報告」
目的 公共の安全確保
対象 主に「荷物用エレベーター」など、建築物に固定された昇降機
建築基準法では、昇降機の所有者は、有資格者(一級・二級建築士または昇降機等検査員)による検査を年1回実施し、その結果を特定行政庁(市や県など)へ報告する義務があります。
これは、設備の劣化や不具合を早期に発見し、公衆への危害を防ぐための制度です。
労働安全衛生法に基づく点検・検査
目的 職場における労働者の安全確保
対象 荷物用エレベーター、簡易リフト(積載荷重0.25トン以上)など、事業場で使用される昇降機
労働安全衛生法では、事業者に対して以下の2つの対応を求めています。
性能検査
国に登録された検査機関による性能検査を受け、検査証の交付を受ける必要があります。
検査証には有効期間(通常1年)があり、期間が切れる前に更新しなければなりません。
定期自主検査
事業者自身の責任において、1ヶ月に1回および1年に1回の定期的な自主検査が義務付けられています。
特に年次の自主検査では、専門的な知識を持つ者に実施させることが推奨されます。
安全管理体制と事業者の責任
法令点検の実施は最低限の義務です。
万が一、点検や整備の不備が原因で労働災害が発生した場合、事業者は厳しい安全配慮義務違反を問われる可能性があります。
事故防止と責任を果たすためには、以下の「予防管理」体制を構築することが極めて重要です。
□法令点検の徹底的な実施と記録保管
□作業開始前の日常点検(異音、動作不良の有無など)のルール化
□操作マニュアルの整備と、作業員への安全教育の実施
□主要部品の交換や仕様変更を行った際の、専門業者や行政への確認・届出
□万が一の事故に備えた、賠償責任保険への加入検討
これらの設備は、事業運営に不可欠なインフラであると同時に、一歩間違えれば重大な事故につながる危険性もはらんでいます。
法令遵守はもちろんのこと、積極的な安全管理こそが、従業員の命と会社の信用を守ることに繋がります。
物件選定時のチェックポイント
貸工場・貸倉庫・売工場・売倉庫を検討する際には、エレベーターのスペック・法令対応・維持状況のチェックが重要です。
□耐荷重やサイズが自社の荷物に適しているか
□荷積みしやすい構造か(フラットな乗入れ、スロープの有無)
□点検記録や整備履歴の有無(未整備物件は要注意)
□保守契約の継続可否や契約条件(年間コストなど)
これらは、長期運用や資産価値維持にも大きく関わる要素であり、見落としがちなポイントでもあります。
導入済み物件の安心感と実務的価値
あらかじめエレベーターや荷物用リフトが導入済みの物件は、賃貸・売買いずれにおいても高評価を得やすい傾向にあります。
省人化・作業効率化
人手不足に悩む現場では、設備の充実が作業負荷の軽減に直結します。
安全性の向上と労災リスクの低減
台車での階段搬送など無理な運搬作業が減り、事故リスクを回避できます。
採用面やBCP(事業継続)対策としての信頼感
安全で効率的な作業環境は、従業員確保や事業継続計画の策定においても強みとなります。
売却時・テナント誘致時の付加価値
エレベーター付き物件は、対象業種が広がるため、投資回収性・資産価値も高く評価されやすくなります。
まとめ
エレベーターや荷物用リフトは、単なる設備以上に、現場の安全性・生産性・将来性に大きく関わる要素です。
導入済み物件はコスト面や維持管理上の安心感も得られ、事業の安定運営に貢献します。
本記事で紹介した知識が、皆さまの物件選びや設備更新のご判断の一助となれば幸いです。
もしお探しの物件でエレベーター設備に関する疑問がございましたら、立和コーポレーションへお気軽にご相談ください。
宅地建物取引業 国土交通大臣免許(3)8600号
◆この記事に掲載の情報は、執筆者の個人的見解であり、立和コーポレーションの見解を示すものではありません。
◆この記事に掲載の情報の正確性・完全性については、執筆者および立和コーポレーションが保証するものではありません。
◆この記事に掲載の情報は、執筆時点のもので、最新の情報ではない可能性があります。
◆この記事に掲載の情報を利用したことにより発生するいかなる費用または損害等について、執筆者および立和コーポレーションは一切責任を負いません。
あらかじめご了承ください。

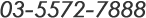
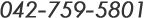
 前の記事
前の記事




