建物の用途ってなに?やさしい言葉で不動産用語を解説
2025/08/07
不動産や建築の話でよく出てくる「建物の用途」という言葉。「住宅」「店舗」「工場」など、なんとなく聞いたことはあっても、詳しく知らないという人は多いかもしれません。
実はこの「建物の用途」、私たちの安全な暮らしと密接に関わる、とても大切なルールなのです。
専門用語をかみ砕きながらわかりやすく解説します。
「こんなはずじゃなかった!」という失敗を防ぐためにも、ぜひご参考にしてください。

目次
建物の用途とは?かんたんに言うと
建物の用途とは、シンプルに言えば「その建物の公式な使いみち」のことです。
建物は見た目が似ていても、「人が住むための家」なのか、「商品を売るためのお店」なのか、「機械が動く工場」なのかによって、守るべき法律のルールが全く異なります。
この「使いみち」を明確に定めているのが、「建物の用途」なのです。
建築基準法で用途が決められている理由
日本では、建物を建てるときに「建築基準法」という法律を守らなければなりません。
そして、この法律の中で建物の用途に関するルールが定められています。
その最大の理由は、「安全で快適な街づくり」のためです。
もしルールがなければ、「静かな住宅街のど真ん中に、夜中まで騒音が響く工場ができてしまった…」といったトラブルが起こりかねません。
また、火災などの災害時に、安全に避難できる設計になっているかも、建物の使い方によって大きく変わってきます。
よく使われる建物の用途の例
住宅(戸建て・アパート・マンションなど)
人が生活するための建物
用途名 専用住宅、共同住宅、寄宿舎など
店舗・サービス系
商品を販売したり、サービスを提供したりする建物。
不特定多数の人が利用するため、住宅よりも避難や防火に関する規定が厳しくなることがあります。
用途名 物品販売業を営む店舗、飲食店、理容店など
事務所・オフィスビル
会社の事務作業を行う建物
用途名 事務所(大きさによっては制限あり)
工場・倉庫など
製品を製造したり、物品を保管したりするための建物。
騒音や振動、においなどが発生する可能性があるため、建てられる場所(エリア)が厳しく制限されます。
用途名 工場、倉庫、自動車車庫など※工場は騒音・においの影響があるため、建てられる場所が限られます。
病院・学校・ホテルなど
人が集まる場所や公共性の高い施設
用途名 病院、診療所、学校、ホテル、劇場、集会所など
※ 避難経路・防火設備などの基準が厳しくなります。
用途が変わるときは「用途変更」の手続きが必要
「住んでいた家を改装して、カフェを開きたい!」
このような場合、建物の「使いみち」が変わるため、原則として「用途変更」という行政への手続きが必要になります。
特に、変更後の用途で使う部分の床面積が200㎡(約60坪)を超える場合は、「建築確認申請」という正式な手続きを行い、現在の法律に適合しているかどうかの審査を受けなければなりません。
無断で用途を変更して営業などをすると、法律違反となり、是正命令や使用禁止命令を受ける可能性があります。
必ず事前に建築士などの専門家に相談しましょう。
用途地域との関係も大切!
建物の用途を考える上で、絶対に切り離せないのが「用途地域(ようとちいき)」という土地のルールです。
用途地域とは、都市計画法に基づき、「そのエリアをどのような街にしたいか」という目的別に土地を13種類に色分けしたものです。
建物の使い方 × 土地の使い方のルールをセットで考える必要があります。
(例) 工業専用地域に、マイホーム(一戸建ての住宅)を建てることはできません。
(例) 第一種低層住居専用地域に、大きなデパート(店舗)を建てることはできません。
まとめ:建物の用途を知って、安全で快適な建物選びを
最後に、この記事のポイントを振り返りましょう。
■建物の用途とは、建築基準法で定められた「建物の公式な使いみち」。
■用途のルールは、安全で快適な街づくりのために不可欠。
■使い方を変えるには「用途変更」の手続きが必要な場合がある。
■「用途地域」という土地のルールによって、建てられる建物の種類が制限される。
建物を購入するとき、借りるとき、あるいはリノベーションを考えるとき。
「この建物の用途は何ですか?」「この土地の用途地域は何ですか?」 この2つを確認することが重要です。
ぜひ「建物の用途」の知識を、建物選びに役立ててください。
宅地建物取引業 国土交通大臣免許(3)8600号
◆この記事に掲載の情報は、執筆者の個人的見解であり、立和コーポレーションの見解を示すものではありません。
◆この記事に掲載の情報の正確性・完全性については、執筆者および立和コーポレーションが保証するものではありません。
◆この記事に掲載の情報は、執筆時点のもので、最新の情報ではない可能性があります。
◆この記事に掲載の情報を利用したことにより発生するいかなる費用または損害等について、執筆者および立和コーポレーションは一切責任を負いません。
あらかじめご了承ください。

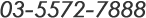
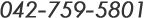
 前の記事
前の記事




