米国追加関税が日本の首都圏の事業用不動産に与える影響を考える
2025/08/06
アメリカによる追加関税の影響で、日本の輸出企業はコスト面で厳しい状況に直面しています。
この影響は、首都圏の事業用不動産市場にも、静かに波及しています。
たとえば、一時的に在庫を多めに確保するために倉庫のニーズが増える一方で、輸出に頼る工場では新たな投資に慎重になる動きも見られます。
公的な統計データをもとに、物流施設・工場・オフィスの3つの分野に分けて、その影響をわかりやすく解説します。

目次
米国の追加関税、いま何が起きているのか?
2025年の夏にかけて、アメリカでは追加関税に関する議論と大統領令の発令が進み、政策の内容が明らかになってきました。
トランプ大統領が導入した追加関税
2025年、トランプ大統領は選挙公約に沿って、大きく分けて次の2種類の追加関税を導入しました。
ベースライン関税 国を問わず、ほぼすべての輸入品に対して一律10%の関税を課す。
相互関税 アメリカに対する関税率をもとに、国ごとに追加関税を設定する。
日米の合意と関税適用の流れ
2025年7月下旬、日米の協議で大きな合意がありました。
日本からアメリカへの輸出品に対し、既存の関税と新しい追加関税(ベースライン+相互関税)を合わせて最大15%までにするという内容です。
この合意を受けて、7月31日に大統領令が発令され、8月7日から適用される予定です。
【物流施設】倉庫の需要が増える一方で、不透明感も
首都圏の物流施設は、2023年からの供給過多の影響で、2025年時点では空室率9%台と高止まりしています。
このような状況の中で、追加関税が新たな変化の要因になっています。
短期的には「在庫を増やす動き」
関税がかかる前に輸出を急ぐ企業や、関税導入後の混乱に備える動きから、一時的に倉庫を借りる需要が高まる可能性があります。
中長期的には「全体の物流量が減るリスク」
コスト上昇を避けるために、輸出入の量を減らす企業が増えると、物流全体の動きが鈍り、倉庫需要が減少する可能性もあります。
これにより、すでに供給が多い市場では、賃料の下落リスクも懸念されます。
【工場】リスクとチャンスが共存する状況に
当初は「工場の投資が鈍る」と予想されていましたが、実際には投資の動きが活発化しています。
数字が示す力強い動き
経済産業省の「工場立地動向調査」によると、2024年の工場の立地面積は前年より28.4%増加。
これは、リーマン・ショック後で最大の増加幅であり、半導体関連の大型投資や、国内回帰の動きが背景にあります。
関税の影響は、ネガティブとポジティブ両面あり
マイナス面 自動車部品など、アメリカへの輸出比率が高い業種では、関税が利益を圧迫し、新規投資が控えられることも。
プラス面 一方で、関税や地政学リスクの高まりから、国内に生産拠点を戻す動きも強まっています。
結果として、投資を控える企業と、あえて国内に投資する企業が混在する中で、国内工場需要が底堅く維持されています。
【オフィス】関税の影響は小さく、都心への回帰が進む
輸出企業の収益悪化は理論上、オフィス需要の減退につながりますが、実際の首都圏オフィス市場は堅調です。
強い需要と低い空室率
2024年から2025年にかけて、東京の主要ビジネス地区では空室率が低下傾向。
本社を都心に集める動きや、より良い働き方を求めたオフィス移転が、その背景にあります。
関税の影響は「一部にとどまる」
輸出企業の業績によって一部影響を受ける可能性はありますが、市場全体では関税の影響はそれほど大きくありません。
むしろ、企業の働き方や拠点戦略の変化が、今の市場を動かしている主な要因です。
まとめ 関税が生む影響と今後の見通し
アメリカの追加関税は、日本の事業用不動産に対して、以下のような影響を及ぼしています。
物流施設 倉庫の一時的な需要増がある一方で、長期的には不透明感が増しています。
工場 輸出に頼る業種には逆風ですが、国内回帰の動きが投資を後押ししています。
オフィス 関税の影響は軽微で、むしろ働き方の変化やデジタル化が市場をけん引しています。
今後のアメリカの通商政策や、それにどう対応していくかによって、これらの動きは大きく変わる可能性があります。
首都圏の事業用不動産市場を考える上では、リスクとチャンスの両面に目を向ける必要があるでしょう。
宅地建物取引業 国土交通大臣免許(3)8600号
◆この記事に掲載の情報は、執筆者の個人的見解であり、立和コーポレーションの見解を示すものではありません。
◆この記事に掲載の情報の正確性・完全性については、執筆者および立和コーポレーションが保証するものではありません。
◆この記事に掲載の情報は、執筆時点のもので、最新の情報ではない可能性があります。
◆この記事に掲載の情報を利用したことにより発生するいかなる費用または損害等について、執筆者および立和コーポレーションは一切責任を負いません。
あらかじめご了承ください。

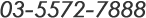
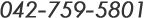
 前の記事
前の記事




