事業用不動産取引と「確定測量」
2025/11/19
~境界リスクを排除し、取引の安全性を確保するために~
工場・倉庫・事業用地などの売買取引において、「この土地はどこからどこまでか」「登記簿の面積は本当に正しいのか」という疑問は、決して軽視できない問題です。
境界や地積の不確かさは、そのまま「資産価値の変動」や「事業計画の狂い」というリスクに直結します。
そこで重要となる手続きが「確定測量」です。
本記事では、事業用不動産の売買を成功させるために不可欠な「確定測量」について、その意味・メリット・実務上の重要ポイントをわかりやすく解説します。
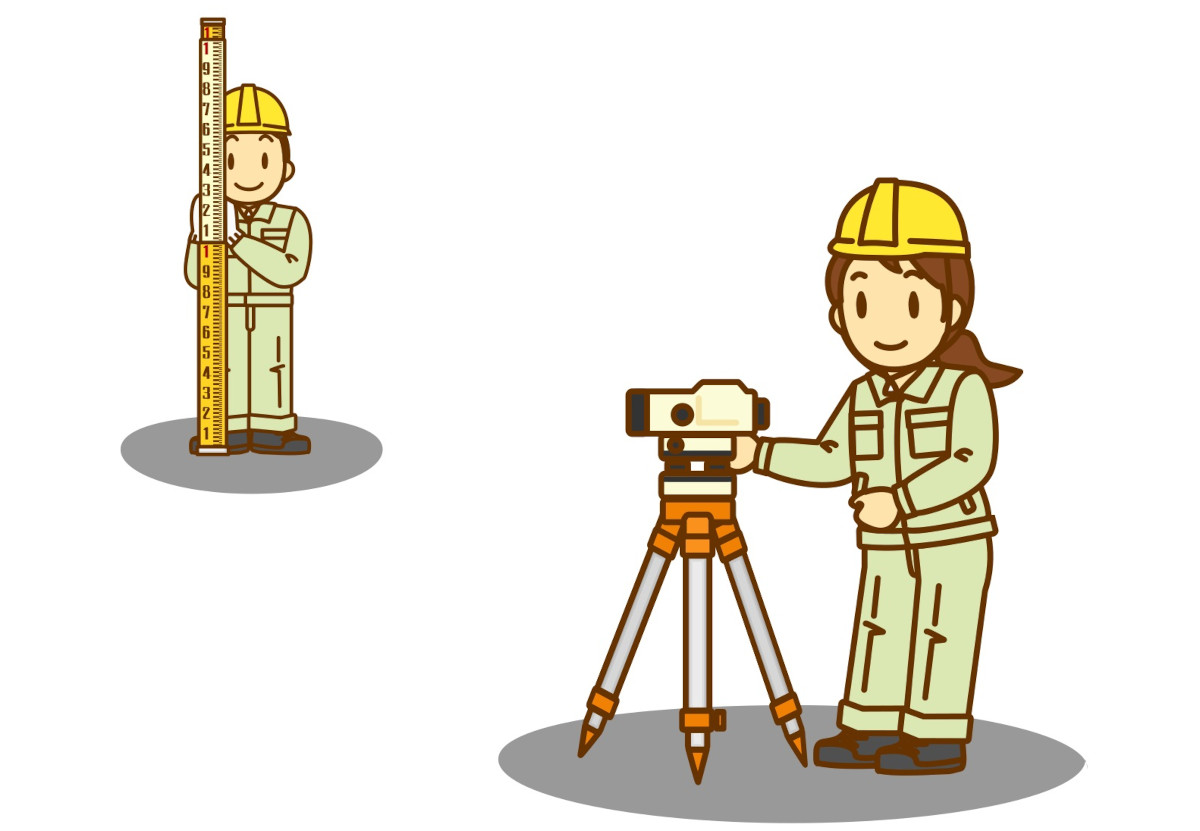
確定測量とは?
基本的な仕組み
「確定測量」とは、隣接地の所有者や、道路・水路を管理する行政担当者に現地へ立ち会ってもらい、関係者全員の合意のもとで境界と面積を正確に確定させる測量のことです。
実務では、主に土地家屋調査士や測量士が中心となり、以下のプロセスで進められます。
現況確認 現地で境界杭や既存の標識を確認
立会い・協議 隣地所有者や行政担当者と現地で境界位置を確認
設置・作成 合意した位置に「境界標」を設置し、「確定測量図」を作成
重要なキーワード:「筆界」と「所有権界」
境界を理解する上で、以下の2つの区別が重要になります。
筆界(ひっかい)
土地が登記された際に定まった、公的な境界線。
「お互いが合意しても勝手には動かせない線」です。
所有権界(しょゆうけんかい)
実際の所有権が及ぶ範囲。
「ここまでは自分の土地だ」と認識している線であり、時効取得や合意によって変わる可能性があります。
確定測量は、登記記録や公図といった資料と、現地の状況、そして隣地所有者との合意(所有権界の確認)をすり合わせ、「公的にも私的にも認められる境界」を確定させる作業と言えます。
「地積測量図」との違いに注意
法務局にある「地積測量図」があれば安心、とは限りません。
確定測量図
特長:隣地所有者の立会い・合意(ハンコ)がある図面。
信頼性:高い(境界紛争リスクが低い)
地積測量図
特長:登記申請時に提出された図面。古いものも多い。
信頼性:まちまち(隣地立会いがない場合もあり、現況とズレていることがある)
「登記簿上の面積」と「実際の面積」が異なるケースは多々あるため、正確な情報を得るには確定測量が不可欠です。
なぜ必要? 事業用不動産における4つのメリット
法的に義務ではありませんが、事業用不動産の実務では「ほぼ必須」とされる理由があります。
① 価格の根拠が明確になる
不動産価格は「単価 × 面積」で決まります。
特に都心近郊の事業用地や、広大な工場用地では、わずか数%の面積誤差が数百万円~数千万円の価格差になります。
実測面積を確定させることで、「買った後に面積が足りないと分かった」といったトラブルや損失を防げます。
② 境界紛争リスクの排除(安心材料)
境界が曖昧なまま購入すると、後から「越境しているから塀を壊してくれ」「ここはうちの土地だ」といった主張を隣地から受けるリスクがあります。
確定測量図があることは、「境界争いがないクリーンな土地である」という強力な証明になります。
③ 建築計画・法令遵守の精度向上
建ぺい率・容積率、斜線制限などの建築基準法は、すべて「敷地面積と形状」が前提です。
もし測量結果が登記簿より小さければ、「予定していた倉庫が建たない」「違法建築になってしまう」という事態になりかねません。
確定測量は、正しい前提条件で事業計画を立てるための土台です。
④ 金融機関・投資家からの評価アップ
銀行の担保評価や、ファンド・リート等のデューデリジェンス(資産査定)において、確定測量図の有無は重要なチェック項目です。
「権利関係が整理されている物件」として、融資や売却時の評価がスムーズになります。
実務で押さえるべき5つの注意点
売買契約に向けて、具体的にどう動くべきかを整理しました。
費用とタイミングの合意
確定測量には数十万円~数百万円単位の費用がかかります。
誰が払うか 一般的には売主負担(または折半)。
いつまでに 決済(引渡し)までに完了させるのが基本。
これらを買付・契約段階で明確にし、契約書に条項として盛り込む必要があります。
最も理想的なのは、「売り出し前、または契約時までに確定測量が完了していること」です。
これにより、境界トラブルのリスクがゼロの状態で安心して取引できます。
スケジュールには余裕を持つ
隣地所有者との調整や行政との協議には時間がかかります。
通常でも1~3ヶ月、難航すればそれ以上かかることもあります。
テナントの退去や土壌汚染調査などと並行して進める必要があるため、無理のない工程管理が重要です。
「実測面積」での精算方法を決めておく
測量の結果、面積が増減することは珍しくありません。
実測売買 実測面積に基づき、売買代金を1㎡あたりの単価で精算する。
公簿売買 登記簿面積で価格を固定し、誤差が出ても精算しない。
どちらを採用するか、事前に取り決めておくことで、測量後の金銭トラブルを防ぎます。
「官民境界」のハードル
道路や水路(官地)と接している場合、役所との立会い(官民査定)が必要です。
これは個人間の確認よりも手続きに時間がかかる傾向があります。
特に、セットバック(道路後退)や払下げが絡む場合は、利用可能面積に直結するため慎重な対応が求められます。
境界紛争の兆候がある場合
「隣地と揉めている」「筆界未定地である」といった事情がある場合、通常の確定測量では解決しないことがあります。
その際は、弁護士等の専門家を入れるか、法務局の「筆界特定制度」を活用するなど、解決への道筋をつけてから取引する必要があります。
おわりに:コストではなく「保険」と捉える
確定測量は、時間も費用もかかる手続きです。
しかし、事業用不動産においては、「将来の法的トラブル」「建築不可のリスク」「資産価値の目減り」を防ぐための、極めて有効な投資(保険)と言えます。
特に、面積が事業の収益性に直結する工場用地・倉庫用地においては、その重要性は計り知れません。
売主・買主双方が安心して取引を進めるために、経験豊富な土地家屋調査士と連携し、早い段階から確定測量の計画を立てることをおすすめします。
宅地建物取引業 国土交通大臣免許(3)8600号
◆この記事に掲載の情報は、執筆者の個人的見解であり、立和コーポレーションの見解を示すものではありません。
◆この記事に掲載の情報の正確性・完全性については、執筆者および立和コーポレーションが保証するものではありません。
◆この記事に掲載の情報は、執筆時点のもので、最新の情報ではない可能性があります。
◆この記事に掲載の情報を利用したことにより発生するいかなる費用または損害等について、執筆者および立和コーポレーションは一切責任を負いません。
あらかじめご了承ください。

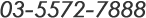
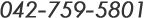
 前の記事
前の記事




