不動産投資を考える(5)市場調査と相場把握の基本
2025/05/05
不動産投資において、「なんとなく良さそう」で物件を選ぶのは非常に危険です。
市場の動向やエリアの相場を把握していなければ、相場より高く買ってしまったり、想定より低い家賃収入しか得られないといったリスクがあります。
今回の記事では、投資判断を支えるための市場調査と家賃・物件価格の相場把握の基本を、客観的な視点から解説します。

市場調査の目的と重要性
適正価格で購入するために
周辺相場を知らずに物件価格を鵜呑みにすると「割高な買い物」になりやすい。
類似物件との比較は、不動産会社任せではなく自分でも行うべき。
将来の家賃収入を現実的に見積もる
想定家賃が相場とかけ離れていると、空室が長期化したり、家賃を下げざるを得ない事態に。
市場賃料をもとに収支計画を立てることが重要。
投資判断の軸を持つ
自分なりの調査データをもとに意思決定すれば、他人の意見に左右されにくくなる。
どんな情報を調べるべきか?
家賃相場(賃貸マーケット)
調べるポイント
同じエリア・築年数・間取り・設備の類似物件の家賃
駅からの距離、階数、方位などによる違い
調査方法
SUUMO、ホームズ、アットホームなどのポータルサイト
地元の管理会社が出している賃貸レポート
成約事例が見られる「レインズマーケットインフォメーション」など
物件価格相場(売買マーケット)
調べるポイント
平米単価や土地価格の推移
過去に売買された実績との比較(成約価格ベース)
調査方法
レインズ(不動産流通標準情報)※取引する不動産会社へ依頼
国土交通省の不動産取引価格情報(実際の成約価格)
ポータルサイトに掲載されている類似物件の価格
利回りの目安
表面利回り=年間家賃 ÷ 購入価格
実質利回り=(家賃収入 − 経費)÷ 購入価格
エリアによる利回りの目安を知っておくことで、想定外の低収益を避けやすくなる
数字だけでなく「需給バランス」も確認する
空室率の高さはリスク
地方都市や供給過多のエリアでは空室率が高く、家賃設定が難航することも。
自治体や不動産会社の統計資料、賃貸住宅新聞なども参考に。
将来の供給計画も視野に
新築マンション・アパートの建設予定が多いと、競合が増え、家賃の下落圧力になる可能性がある。
建築確認申請情報や開発計画を自治体サイトで確認可能な場合も。
取引する不動産会社や管理会社から得られる情報
成約家賃や入居者の傾向は、ネットより現場に詳しい管理会社の方が把握していることが多い。
客付けしやすい間取りや設備、水回りリフォームの効果など、実務的な感覚をヒアリングできる。
※ ただし特定の物件を売るためのポジショントークでないかは、慎重に見極めること。
調査データをどう活用するか
収支計画に反映
想定家賃・管理費・空室率・修繕費などをすべて市場実勢に基づいて計算。
複数シナリオ(ベース・楽観・悲観)を準備しておく。
融資交渉や購入価格交渉の根拠に
「相場と比べて割高」であることを根拠に、価格交渉ができる材料になる。
銀行への事業計画提示時にも信頼性が増す。
まとめ
不動産投資では、物件自体の良し悪しだけでなく、「その価格や家賃が適正か」を見極める力が求められます。
相場や利回り、需給バランスなどを調査し、数字の裏付けをもって判断することで、リスクを抑えた投資が実現しやすくなります。
現地の管理会社や統計データなど、複数の情報源を活用しながら、冷静に相場を読み解いていきましょう。
宅地建物取引業 国土交通大臣免許(3)8600号
◆この記事に掲載の情報は、執筆者の個人的見解であり、立和コーポレーションの見解を示すものではありません。
◆この記事に掲載の情報の正確性・完全性については、執筆者および立和コーポレーションが保証するものではありません。
◆この記事に掲載の情報は、執筆時点のもので、最新の情報ではない可能性があります。
◆この記事に掲載の情報を利用したことにより発生するいかなる費用または損害等について、執筆者および立和コーポレーションは一切責任を負いません。
あらかじめご了承ください。

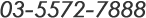
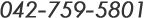
 前の記事
前の記事




