不動産投資を考える(3)自己資金と資金計画をどう立てるか
2025/04/23
自己資金の把握と資金計画は、不動産投資の持続性を左右する土台です。
頭金にいくら充当できるのか、どこまで借入に頼るのか、そして購入後のランニングコストをどう捉えるのか――これらを具体的に数値化することで、投資全体のリスクを可視化し、長期的なキャッシュフローを安定させることができます。
本記事では、評価的かつ客観的な視点から資金面の検討プロセスを整理します。
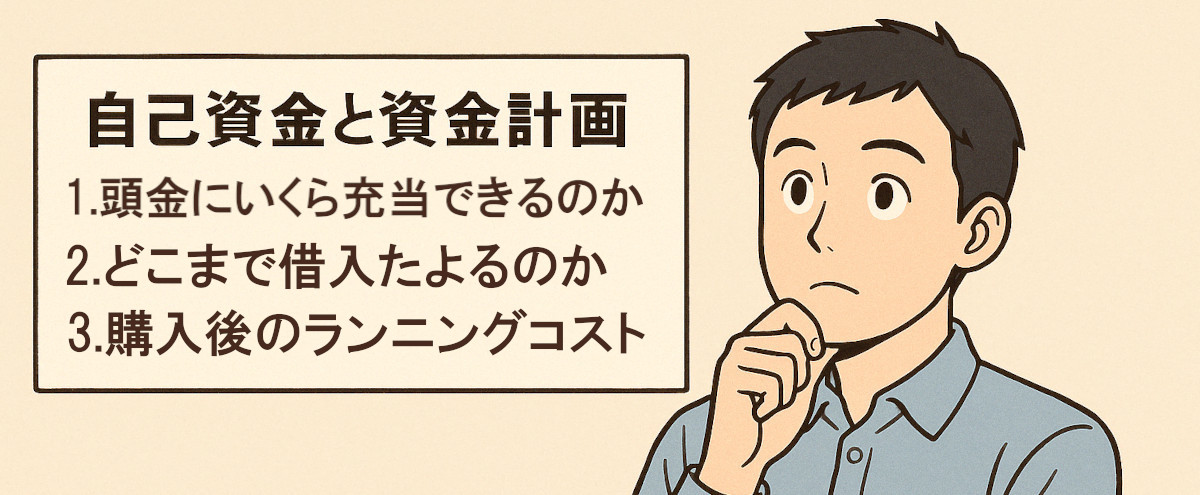
自己資金を正しく把握する
頭金の目安と生活防衛資金
頭金比率 金融機関が求める目安は物件価格の10〜30%前後が一般的。自己資金を多く投入すれば毎月返済額が下がり、金利交渉力も高まります。
生活防衛資金 投資に充当しない緊急資金を別口座に確保しておくことで、突発的な支出にも耐えられます。
自己資金の源泉を整理する
現預金 流動性が高く即時投入可能。
金融資産の売却 株式・投信の売却益を充てる場合は税負担も試算。
親族支援や贈与 贈与税の基礎控除や相続時精算課税など税務面を要確認。
自己資金を増やす方法
投資開始時期を延ばして貯蓄を厚くする
不要資産の売却や固定費削減で投資余力を高める
ふるさと納税やiDeCoなどの節税策で可処分所得を拡充
融資計画の基本
借入可能額を試算する指標
年収倍率 年収に対していくら借りられるか 8〜12倍
返済負担率 年収に占める年間返済額の割合 25〜35%
与信スコア 勤務先・勤続年数・信用情報など 銀行ごとに評価基準
金利タイプと返済期間
固定金利 返済額が読みやすいが、変動より金利は高め。
変動金利 金利上昇局面のリスクをストレステストで確認。
返済期間 長期にすると月々の返済負担は軽減できるが、総返済額は増加。
返済シミュレーションの3ポイント
毎月返済額 表面利回りだけでなく手取りキャッシュフローと比較。
総返済額 金利・期間・繰上返済有無で大きく変動。
ストレステスト 金利+1〜2%上昇や空室率悪化を想定し、耐性を確認。
購入後に発生するランニングコスト
管理費・修繕積立金・固定資産税
区分所有マンション 管理費+修繕積立金が月額5,000〜20,000円程度。
戸建・一棟物件 大規模修繕費を10〜15年ごとに一定割合で積み立てておく。
保険料・共用部光熱費など
火災保険・地震保険は金融機関が条件とすることが多い。
共用部電気・清掃費は管理形態(自主管理/委託)でコストが変動。
突発修繕費のバッファ
給排水配管や屋上防水など、築年数が進むほど突発修繕が発生。
年間家賃収入の5〜10%を目安に内部留保を設定すると安心。
長期キャッシュフロー設計
想定家賃収入と空室率
家賃設定 周辺相場と築年数・設備を踏まえて保守的に見積もる。
空室率 保守シナリオとして5〜10%を想定し、感度分析を実施。
NOI(営業純利益)計算
NOI = 年間賃料収入 - 空室損 - 運営費(管理費・修繕費・保険料 等)
キャッシュオンキャッシュリターン(CCR)
CCR = 税引前年間キャッシュフロー ÷ 投下自己資金
投資効率を示す指標として、自己資金のどれだけが年間キャッシュとして回収できるかを可視化。
リスクシナリオとバッファ設定
金利上昇シナリオ
金利+2%でもプラスキャッシュフローを確保できるか検証。
空室率悪化シナリオ
想定空室率を20%に上げても返済が滞らないか試算。
自然災害・大規模修繕
耐震診断やハザードマップで災害リスクを把握。
大規模修繕資金は少なくとも築後10年時点から積立を開始。
資金計画チェックリスト
□ 頭金比率と生活防衛資金の分離
□ 年収倍率・返済負担率の範囲内か
□ 金利タイプと返済期間の選択根拠
□ ランニングコストの保守見積もり
□ 空室・金利ストレステストの実施
□ 突発修繕費用のバッファ設定
まとめ
自己資金の把握と資金計画は、不動産投資における安全余裕度そのものです。
頭金、借入、ランニングコスト、そしてリスクバッファを定量的に示すことで、長期キャッシュフローがブレない投資シナリオを描けます。
宅地建物取引業 国土交通大臣免許(3)8600号
◆この記事に掲載の情報は、執筆者の個人的見解であり、立和コーポレーションの見解を示すものではありません。
◆この記事に掲載の情報の正確性・完全性については、執筆者および立和コーポレーションが保証するものではありません。
◆この記事に掲載の情報は、執筆時点のもので、最新の情報ではない可能性があります。
◆この記事に掲載の情報を利用したことにより発生するいかなる費用または損害等について、執筆者および立和コーポレーションは一切責任を負いません。
あらかじめご了承ください。

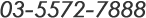
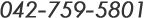
 前の記事
前の記事




